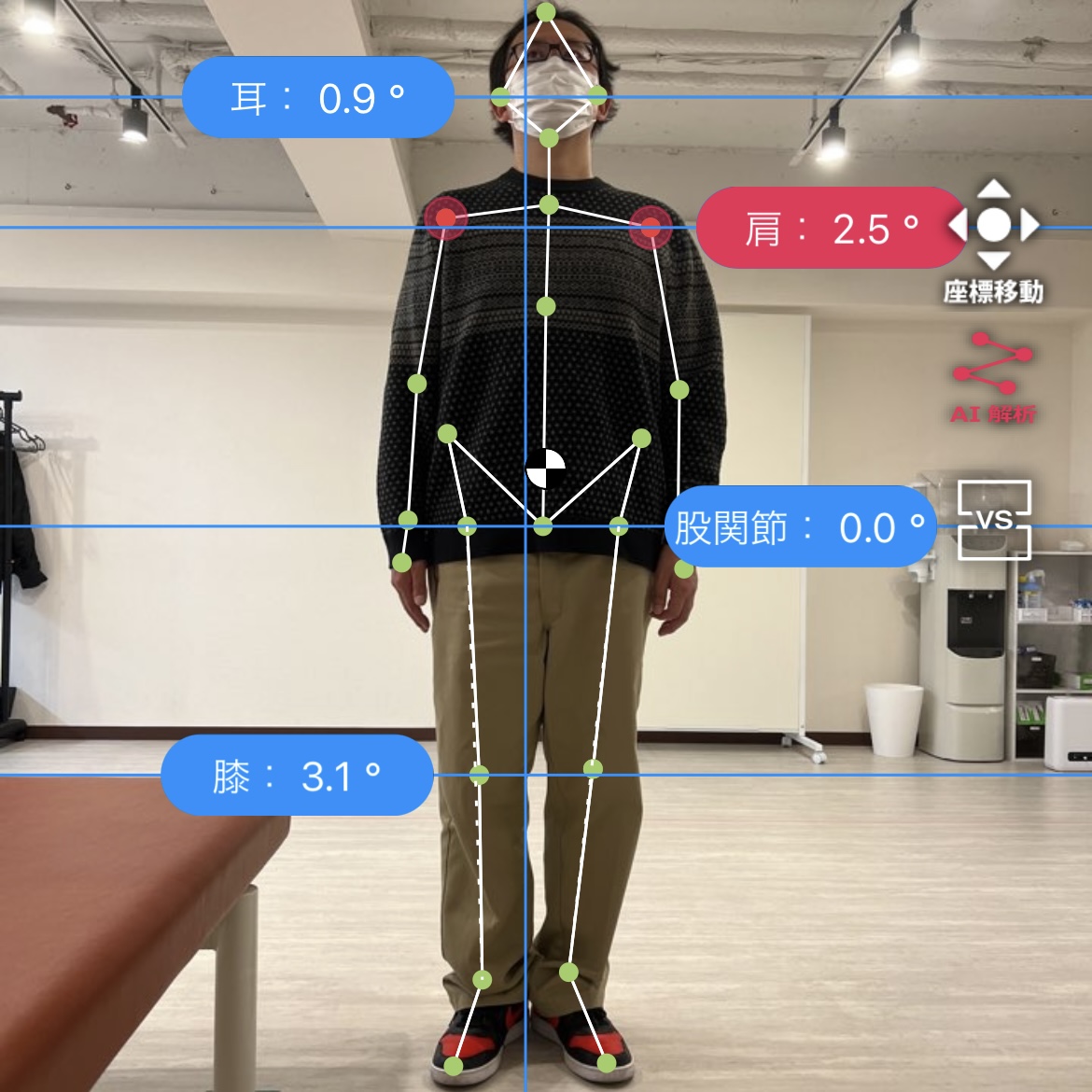2024 年 4 月 13 日公開
高次脳機能障害の克服②
高次脳機能障害の克服
今回のブログでは、脳梗塞や脳外傷後に生じやすい注意障害 に対し、種類や特徴、そして症状を改善させる取り組みを述べていきます。.
高次脳機能障害① で挙げた症状の中でも、上位に挙げられるのが、注意障害です。注意障害によって引き起こされる症状は、4種類に大きく分けられます。
①持続性(sustained)
①の持続性は、一定時間、集中して作業を続ける機能です。持続性の低下が認められる場合は「疲れやすく、同じ作業に注意を向け続けることが困難である」「集中して継続することが困難である」といった症状がみられます。
②の選択性は、目の前にある多くの情報から選択して、注意を向ける機能です。選択性の低下がみられると、「周囲の音や人に注意がいってしまい、行うべき作業を、集中して行うことができない」といった症状がみられます。
③の転換性は、一つのことに集中していても、別のことに気づき、注意を切り替えることができる機能です。注意の転換が困難な場合、例えば「一つの作業を行っているところに、電話がかかって来ても気づけない」といった症状がみられます。
④の分配性は、一つのことだけでなく、二つ以上の物事に注意を配る機能です。二重課題を同時進行で行うことができない場合、注意の分配が行えていないと言えます。困難な場面としては「転ばないように気をつけて歩くことに精一杯で、隣にいる人と会話ができない」のような例があります。
脳梗塞の急性期における注意障害は、意識レベルの改善とともに、同じく改善されることが多いです1)。注意障害の評価は、机上での検査や、行動評価など、各評価バッテリーの点数を使用することで、より客観的に経過を追うことが可能です。
また、実際の生活場面で、出来るようになったことを増やすといった経過評価を行うことも可能です。代表的な検査は以下の通りです。
机上での検査
・標準注意検査法(CAT : Clinical Assessment for Attention)
・TMT(Trail Making Test) 【図1】
行動評価
・RSAB(Rating Scale of Attention Behaviors)
・BBAD(Behavior Assessment of Attention Disturbance) 【図2】
図1: TMT(Trail Making Test) Part A, Part B
図2: BAAD(Behavioral Assessment for Attention Disturbance)の内容と採点
注意障害のアプローチ 各注意障害に対してのアプローチ方法は以下のような形になります。①持続性低下 ②選択性低下 ③、④転換・分配性低下 .
リハビリベース国分寺で注意障害に対してアプローチする際には、脳画像から起こりうる障害の予測などを行い、利用者様やご家族様への生活場面に対してのインタビューと、実際の身体機能の評価を照らし合わせることによって、細かく症状を評価、分析していきます。身体機能の評価に関しては、具体的には、バランスや眼球運動、実際のリハビリ課題下での注意評価があげられます。
リハビリの内容に関しては、リハビリベース国分寺では、一回の訓練を90分に設定しています。この90分の中で、理学療法士による徒手としゅ 的な治療と、難易度を徐々にあげながらの動作訓練を中心に行っていきます。90分は集中できる持続的注意としても、難易度の高い時間ですが、ご利用者様ひとりひとりに合わせて難易度を調整することで、可能な注意課題の幅を、少しずつ増やしていきます。
リハビリによって実感できる変化は人によって異なりますが、例えば、自宅内で「自発的な活動が増える」「会話が多くなる」「周囲の変化に気づきやすくなる」といったことがあげられます。
屋外での活動は、自宅内の活動と比較すると、情報量の多さや注意課題の難易度が大きく変わってきます。それぞれの移動形態や歩行レベルにもよりますが、「移動すること」「人や車に対して道を譲る」「避ける」「周りを見てバランスを取りながら歩く」など、難易度が高いものとなってきます。
高次脳機能障害を持つ方にとって、屋外での活動は大きなハードルとなることもありますが、同時に、外へ出る楽しさを感じられるようになって、目標を達成する上で、大きな分岐点になることもあります。
リハビリベース国分寺では、高次脳機能障害をお持ちの方に対しても、現状の身体機能の評価やご本人との対話を多く持つことによって目標を共有し、実際にできる活動を増やしていきます。リハビリを受けられる日数などに制限がある保険適用リハビリでなく、自費で行うリハビリのため、ひとりひとりのお悩みや目標に寄り添うことが可能です。
『50代男性 脳出血後、復職への道のり』
こちらでは、屋外歩行と復職を目標とされた方のリハビリをご紹介しております。当施設でのリハビリの流れが分かる内容となっておりますので、ぜひ、こちらもご覧ください。
【引用文献】
1) 豊倉穣.(2008). 注意障害の臨床. 高次脳研究28(3):320~328.
高次脳機能障害の克服
脳梗塞や、脳外傷後に生じやすい注意障害に対し、種類や特徴、そして症状を改善させる取り組みを述べていきます。.
高次脳機能障害① で挙げられた症状の中でも、上位に挙げられるのが、注意障害です。
注意障害とは、どのような症状があり、日常生活において、どのような支障を来してしまうのでしょうか。
注意障害は、大きく分けて、代表的なものが4種類挙げられます。
①持続性 (sustained)
①の持続性は、一定時間、集中して作業を続けることができる注意機能です。低下が認められる場合として、疲れやすく同じ作業に注意をむき続けることが困難であることや、集中して継続することが困難な状態がみられます。
②の選択性は、目の前にある多くの情報から、選択して注意を向ける機能です。低下がみられると、周囲の音や人に注意がいってしまい、行うべき作業を集中して行うことができない、といった症状がみらます。
③の転換性は、一つの注意に集中しているところ、別のことに気づき注意を切り替えることができる機能です。注意の転換が困難な場合の例としては、一つの作業を行っているところ、電話がかかって来ても気づけない、といった症状がみられます。
④の分配性は、一つのことだけでなく、二つ以上の物事にも注意を配る機能です。困難な場面として、転ばないように気をつけて歩くことに精一杯で、隣にいる人と会話ができないと言ったことが見受けられます。このような二重課題を同時進行が行えない場合に、注意の分配が行えていないと言えます。
.
脳梗塞の急性期における注意障害は、意識レベルの改善とともに、同じく改善されることが多いです1)。注意障害の評価は、机上での検査や、行動評価など、各評価バッテリーの点数を使用することで、より客観的に経過を追うことが可能です。また実際の生活場面で、出来る様になったことを増やすといった経過評価を行うことも可能です。机上の検査で代表的なものとしては、標準注意検査法(CAT : Clinical Assessment for Attention)、図1のTMT(Trail Making Test)があり、行動評価としては、RSAB(Rating Scale of Attention Behaviors)、図2のBBAD(Behavior Assessment of Attention Disturbance)が代表的なものとして挙げまれます。
図1: TMT(Trail Making Test) Part A, Part B
図2: BAAD(Behavioral Assessment for Attention Disturbance)の内容と採点
各注意障害に対しての、アプローチ方法を以下に述べていきます。①持続性低下 ②選択性低下 ③、④転換・分配性低下 .
リハビリベース国分寺で行う、注意障害に対してのプロセスとしては、脳画像から起こりうる障害を予測します。
リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?