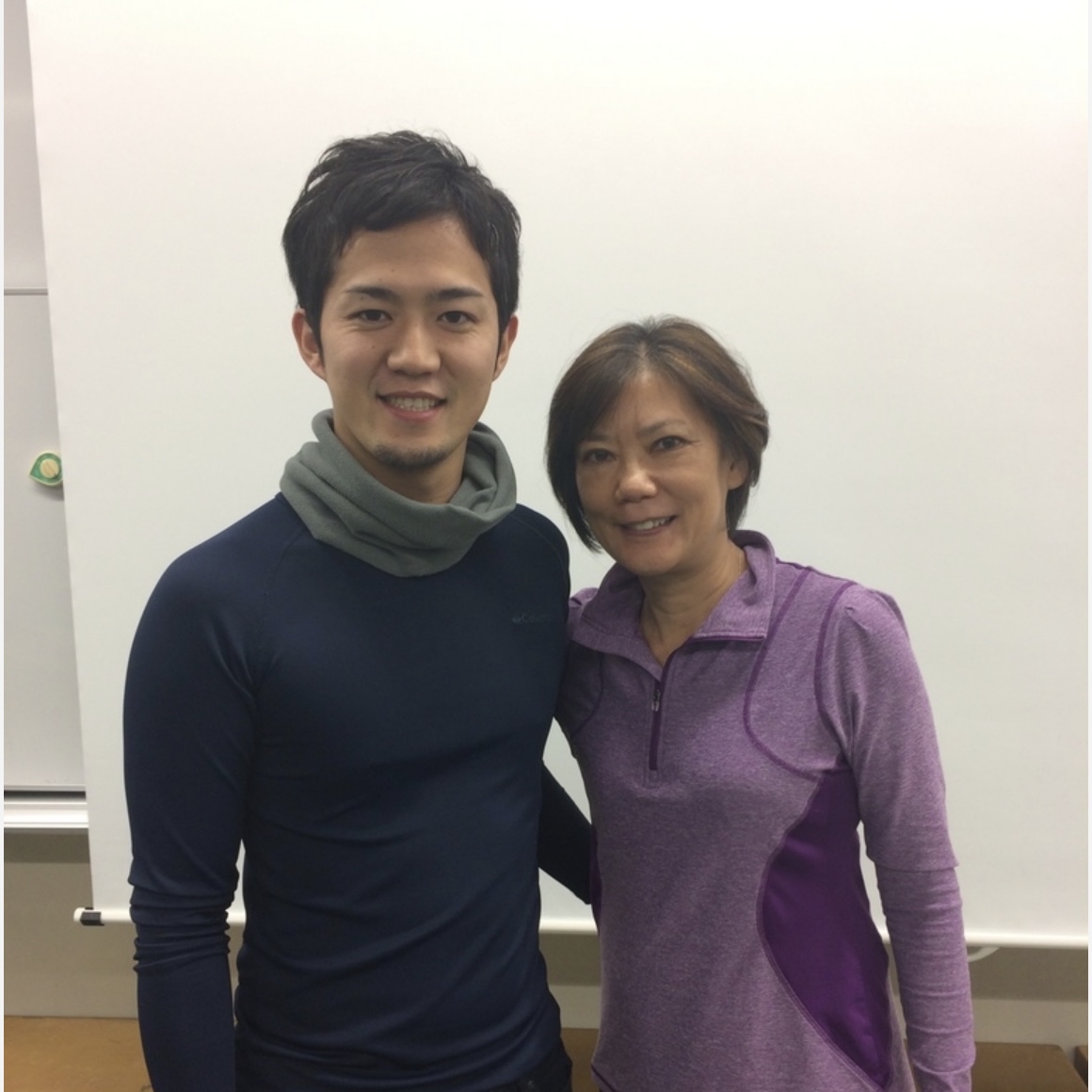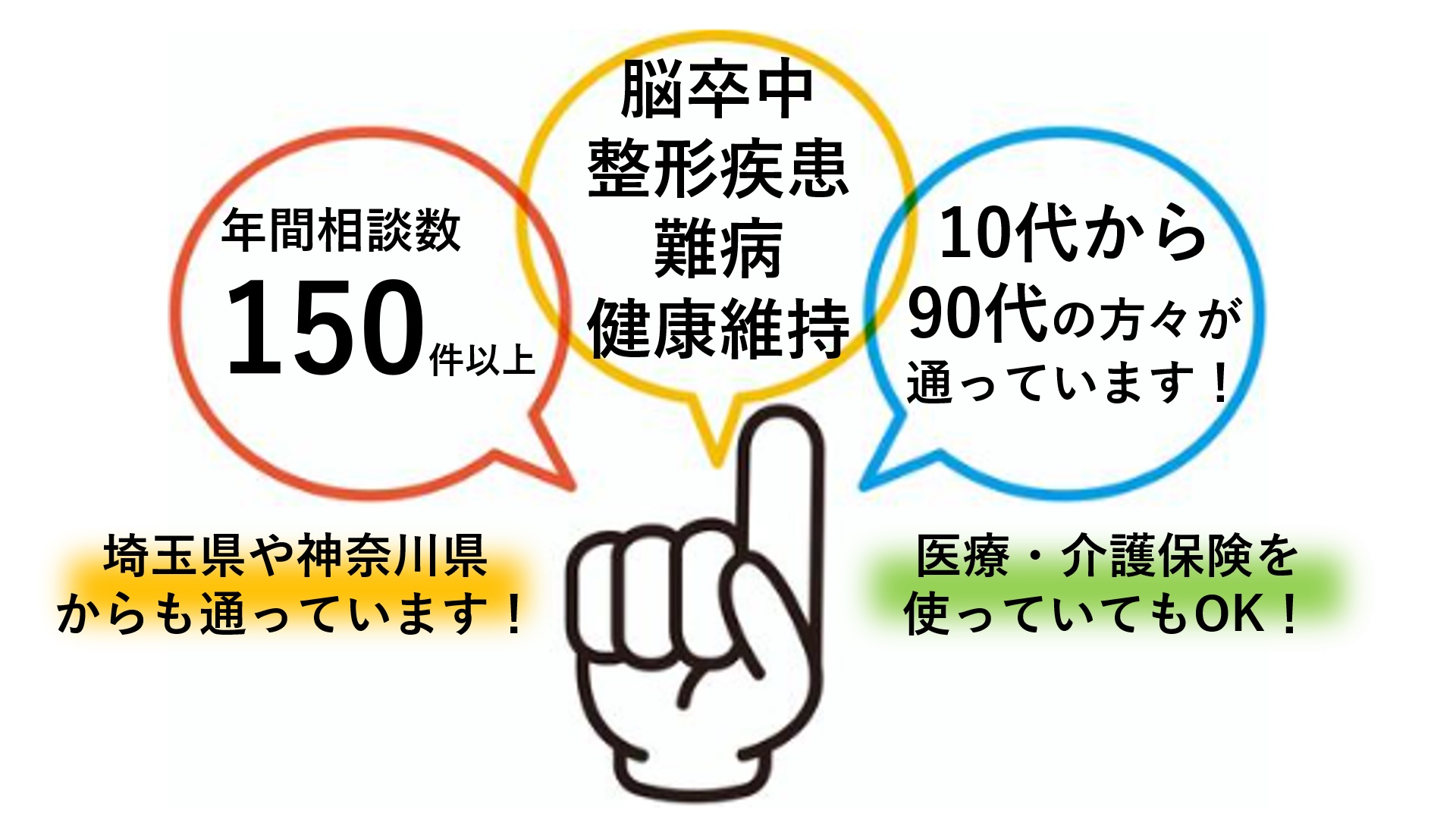筑波大学と共同開発された2億円の動作分析機器と同等レベルの評価が可能な最先端AIシステムです。動作や姿勢の評価において、指導者側の経験や感覚に依存した指導が行われているのが現状です。それぞれの、個人の身体特性・データ・目的に応じてITの力を駆使し、適切な指導を届けることが出来ます。
リハビリベースではリハビリ開始時と最後だけではなく、その日のBefore/Afterも可視化することが出来ます。

IVES®は筋肉の動きを電気信号(筋活動電位=筋電)として読み取り、動きに応じた電気刺激を筋肉にあたえるものです。少しだけ動かしたら弱い刺激が、大きく動かしたら強い刺激が入ります。一般的な低周波治療器に多い、あらかじめ設定した電気刺激を一定量送り続ける仕様とは異なり、日常の中で自分の筋肉の力で治療をサポートします
自己意思に基づく動きを「随意運動」といいます。随意運動では手足などの身体は脳からの運動指令が神経を通って筋肉に伝えられて初めて動きます。脳梗塞などの後遺症のリハビリに効果的です。

大手ヘルスケアOMRON社が開発したコードレス低周波治療器です。
リハビリベースでは低周波モードで部分的な筋肉の刺激、浮腫の改善、筋の促通など行います。また、電気刺激を入れたまま運動いたします。疲労が強いところにはプロアスリートも使用する「マイクロカレント」も用います。マイクロカレントは通常刺激を感じることはない、ごく微弱な電流を使った治療です。

日本理学療法士協会が定める生涯学習制度の中で、国民に対して理学療法士という専門職の質を保証するための認定制度です。「5年ごとの更新制」を取り入れることで、生涯にわたり知識・技術の維持・向上が可能となり、より専門性の高い臨床技能を有する「スペシャリスト」です。理学療法士の免許は2022年には約20万人の有資格者がいますが、認定理学療法士を持っているのは5%しかいません。

Dynamic Neuromuscular Stabilizationの略で、日本語では「動的神経筋安定化」と呼ばれています。 赤ちゃんが歩くまでの1年間の正常な発達運動を基礎にした動作の安定性と運動制御“モーターコントロール”に着目したリハビリテーションアプローチです。脊柱の安定性(体幹の安定性)は、横隔膜の機能を利用して高め、手足の運動、起き上がり、歩行、スポーツ動作などすべての動作において重要な役割を果たします。研究においてもその効果が認められています。DNSは世界的にも有名で、スポーツ分野で話題となることが多いです。

非対称な姿勢や動作をとり続けることや同じ姿勢を長時間とり続けること、怪我などによって身体の一部に負担がかかり、身体がアンバランスな状態となると筋膜が自由に動けない状態になります。すると筋膜のよじれが生じて筋膜と皮膚・筋肉との間の滑らかな滑りが失われます。筋膜は全身につながっているので、ほかの筋肉や筋繊維にまで動きの悪さが波及し、痛みや筋力の低下、柔軟性の低下、運動パフォーマンスの低下、日常生活活動の低下がみられるようになります。筋膜のよじれやねじれを解消して、正しい筋と筋膜の伸長性と筋肉の動きの回復を促すのが筋膜リリースです。筋膜リリースはストレッチのようにある一定の方向に伸ばすのではなく、筋膜をさまざまな方向に解きほぐしていくことです。本来は理学療法士などが筋膜リリースを施術します。

足底板(インソール)とは、靴の中敷きのことで、靴の歴史が長いヨーロッパ諸国では古くから使用されてきました。従来は、足底板に凹凸をつけることで、足部のアーチの低下を防いだり、足部の安静、矯正を目的として使われてきました。作製方法に至っては、主に足だけを診て、座位や立位で足型をとって作製する静的製法が用いられてきました。
入谷氏が考案した入谷式足底板は、足にテーピングやパッドを用いて足部形状を変化させ、足部だけでなく、身体の姿勢や動作を確認しながら作製するという画期的な製法で、いわば動的製法ということができます。入谷氏の考案したこの製法は、足底板を作製する前に足部の形状やアーチの高さを検査することでより個々に適応したオーダーメイドの製法といえます。
入谷氏のもとには、多くのプロ野球選手、五輪選手、Jリーガー、海外プロスポーツ選手等々、従来病院で処方されていた足底板の範疇を超え、多くのスポーツ選手、著名人が入谷氏のもとを訪れました。
![]()
イギリスの医師である故カレル・ボバース博士と理学療法士のベルタ・ボバース夫人により開発された、リハビリテーション治療概念のひとつです。脳や脊髄といった中枢神経系の可塑性を活用し、中枢神経疾患に起因した障害をもたれた方々の機能改善をめざす治療です。1940年代に始められ、その後、世界各地で多くの指導的立場の療法士を輩出し、さらに治療内容を発展させながら世界的に普及しています。
![]()
PNFは本来、脳血管障害や脳性麻痺などによる神経障害、筋力低下、協調不全、関節可動域制限などの改善または、日常生活に必要な運動機能を獲得、向上させるために、目的とする生体反応を引き出す治療法ですが、現在では、体全体の筋バランス、柔軟性、敏捷性、持久力、反応時間、運動能力の低下など運動機能の改善と向上に応用され、高度なスポーツ技術の獲得、向上のためのSkill(巧緻性)にも応用できることから、一般臨床だけでなくスポーツの分野でも幅広く用いられるようになっています。
![]()
神経モビライゼーション(以下NM)とは末梢神経系の感受性,伸張性,運動性を改善する手技であり,その目的には疼痛やしびれの改善,二次的障害の予防がある。
![]()
ヤンダ(本名ブラディミア・ヤンダ)とはチェコの神経学者であり、医学部を卒業後、理学療法士を志し、セラピーと医学を結びつけたアプローチを行う最初の医師である。そのため、彼のことを「リハビリテーションの父」と呼ぶ。ヤンダが考案したヤンダアプローチとは、従来の解剖学や生体力学に基づいた身体構造の損傷に対する構造的アプローチとは対照的である。感覚システムおよび運動システムの障害によって起こる機能障害に着目し、これにより生じるマッスルインバランスに神経・筋骨格系からアプローチする治療である。