お知らせ・ブログ
-

-
営業時間 9:00~18:00月~金(定休日:土日祝祭日)
042-401-0890 - 体験・予約・お問合せ
営業時間 9:00~18:00月~金(定休日:土日祝祭日)
042-401-0890お知らせ・ブログ
すっかり過ごしやすくなり、公園などで、子どもがかけっこやボール遊びをする様子が見られるようになりました。風も気持ち良く、運動にはうってつけの季節ですね。
ところで、小・中学校の「運動会」と「体育祭」の違いは、ご存じでしょうか。
厳密な定義はないようですが、基本的には、目的や運営主体によって使い分けがされます。学校や会社が主体となって行い、運動競技や遊戯を楽しむ目的で行われるのが「運動会」。中学校・高校などで、生徒自身が主体となって、授業の成果を発揮するために行うものが「体育祭」です。
以下の文章では運動会と書きますが、今回の記事で紹介する運動は、年齢に関わらず行うことができます。
また、運動会は何月頃に行われるイメージをお持ちでしょうか。
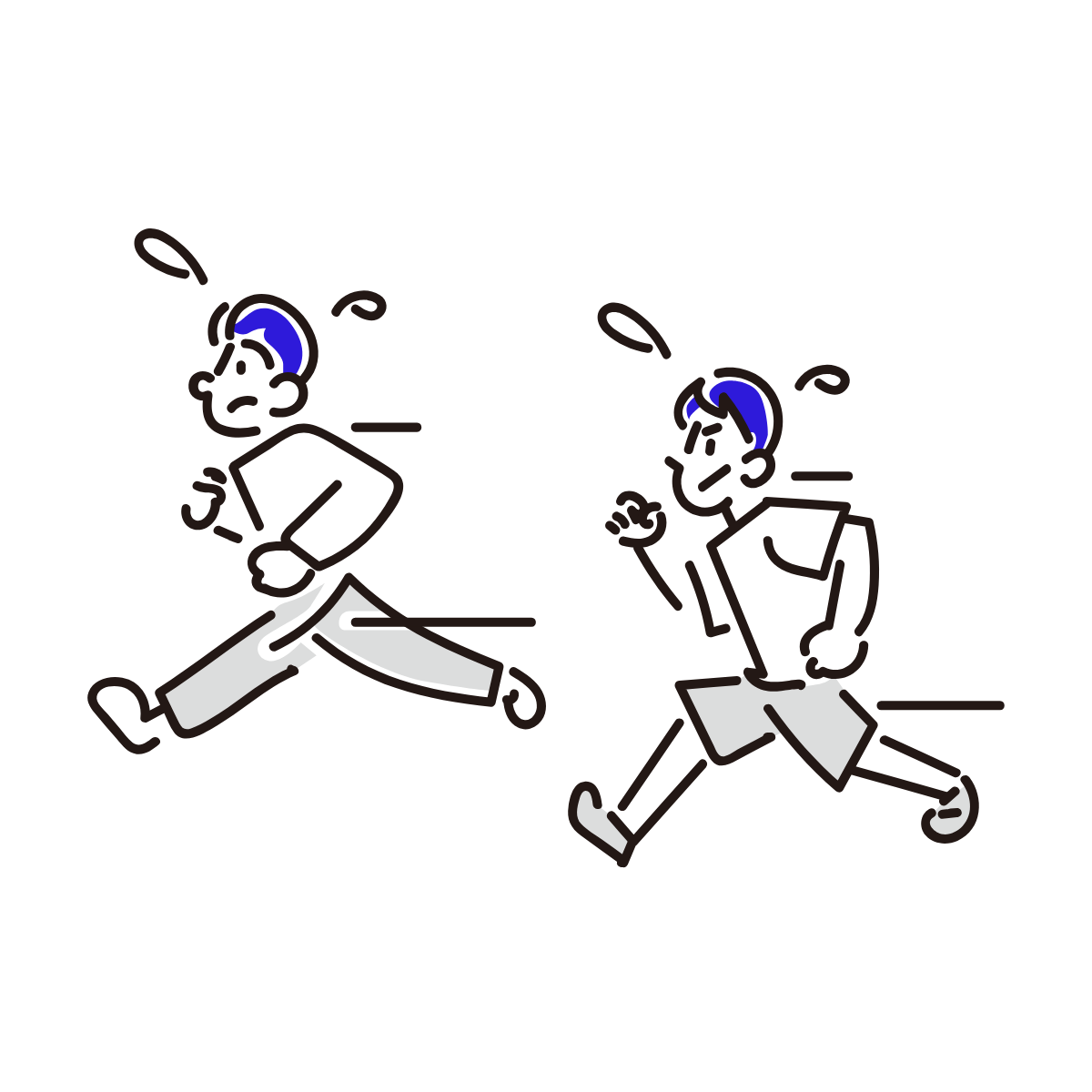
1964年の東京オリンピックが10月に行われたことから秋頃に行う学校も多く、秋頃開催のイメージをお持ちの方も多いでしょうが、現在では、どうやらわずかに春開催の方が多いようです。
春開催が増えた理由の一つには、熱中症対策があります。ただし現在では、体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」によって、秋の方が熱中症になりにくくなるという情報もあります。
今後、当院のブログでも、熱中症や夏の運動の注意点などについてもお伝えする予定ですが、5月から熱中症にはご注意ください。
運動会の開催時期には地域性もあり、例えば、北日本では昔から春開催が多く、西日本では秋開催が多いそうです。住んでいる場所によっても、実感は異なるかも知れません。ちなみに国分寺市では、5、6月に行う学校が多いようです。
現在、多くの小・中学生は、運動会に向けて一生懸命に練習をしています。
そんな子どもたちに負けずに、あるいは仲良く一緒に、周囲の大人も運動不足を解消するリハビリとして、トレーニングをするのはいかがでしょうか。
今回は、子どもと一緒にできるトレーニングを紹介いたします。競い合ったり、励まし合ったりして、リハビリを楽しんでください。
夏の風物詩であるラジオ体操。早朝に起きて、眠い中で体を動かした覚えのある方もいるでしょうが、これが実は全身を動かすことのできる、とても良い運動だということをご存知でしょうか。
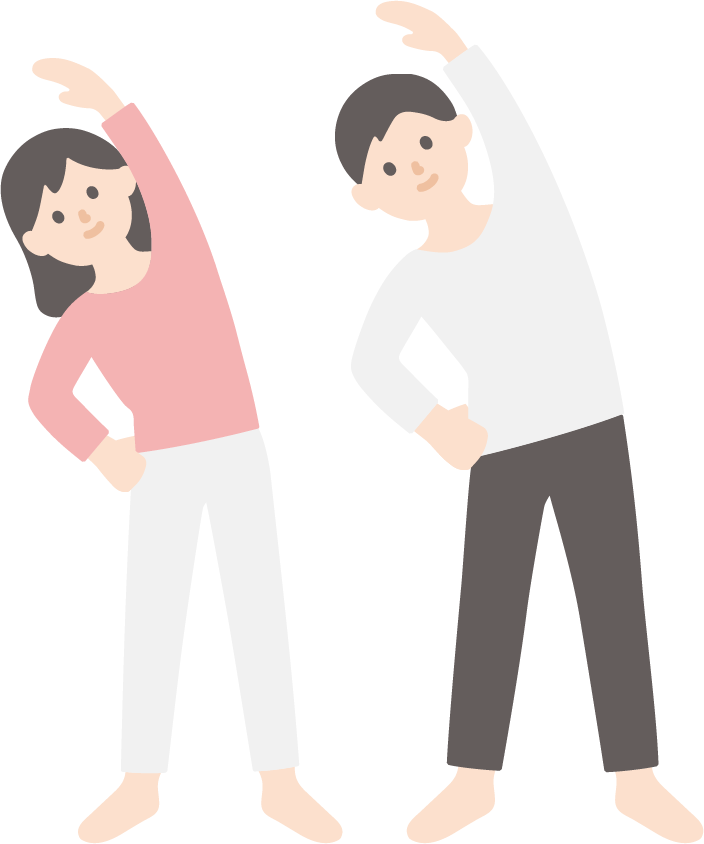
準備運動として、体育の前にラジオ体操を取り入れている学校も多くあります。準備運動は筋肉の動きをスムーズにしたり、関節の可動域を広げることで、怪我を予防します。
また、全国ラジオ体操連盟によれば、「朝の全身運動は脳や中枢神経の働きをよくし、子どもの集中力や行動の安定性にも役立つます。より良い生活習慣の確保や身体育成、姿勢の保持、準備運動による身体の怪我等の防止、整理運動による健康保持等にも役立ちます(後略)」とのことで、普段の生活にも良い影響を期待できます。
当院の院長も、介護予防や転倒予防教室で「ラジオ体操はやってます。おすすめですか」という質問をされるそうですが、必ず「オススメです!」と答えるそうです。
それは、日々継続できて、家族や友人と一緒にできる。また、ご自身の『今日の健康チェック』にもつながることが理由とのことです!
ラジオ体操は椅子に座って行うこともできますし、音楽に乗って体を動かすことで、認知症予防も期待できます。
また、家で運動をする時には、準備運動を忘れてしまう子どももいます。
声かけをして、一緒にやってみてはいかがでしょうか。
ご家庭に、縄跳びのような、少し長さのあるロープ状のものはあるでしょうか。床にまっすぐに伸ばせば、バランス能力を鍛えることのできる、簡易的な平均台を作ることができます。
バランス能力は、走る時の姿勢を正しくキープする時や、不安定な状態から転ばないように素早く体を戻す時に大切になってきます。普段の生活で、座って落ち着いて授業が受けられないという子どもも、実はバランス能力が不足している場合があります。
また、視点を前方に固定して、ロープの感触を頼りに歩くことで、足の裏で地面を探る感覚を身につけることができます。歩きに不安が出てきた方も、試してみてください。
運動会と言えば、徒競走を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。100メートル、1200メートルなど距離は様々で、距離に応じた競技性の違いもありますが、どんな距離であっても「足の速さ」は重要な要素の一つです。
徒競走だけでなく、リレーや障害物競走など「速く走れること」が結果を変える競技が、運動会では多々あります。「もっと速く走れるようになりたい」と思う子は、少なくありません。
走るのは難しい、という方でも、子どもと一緒にトレーニングする方法があります。
紹介するのは、速く走る時に重要な力の一つ、「地面を押す力」を鍛える2つのトレーニングです。
地面を押す時には「しっかりと地面をとらえる」ことが大切になります。単に押すだけでは、足が後ろに滑り、前に進むための反発力が逃げてしまい、地面を押した力を充分に利用できないこともあるためです。そのため、地面をとらえるためには、「足指の力」を鍛えることが重要になってきます。
足の指を鍛える方法の1つ目は、「足の指を使ったじゃんけん」です。足の指を丸めてグー、開いてパー、親指のみを広げるチョキで行います。
2つ目は、「足の指でタオルをつかんで引っ張る」という方法です。床などにタオルを広げて、その上に足を置き、足の指の力で、広げたタオルをくしゃくしゃとまとめていってください。
2つとも、椅子に座りながらでもできるトレーニングです。麻痺で指が動かしづらい時のトレーニングとしても効果的です。一緒にぜひやってみてください。

いかがでしょうか。コロナも経て体育際の様子も少しづつ変化しているところもある思いますが、ケガを予防して、子供と一緒にリハビリ?トレーニング?を行い、楽しい思い出ができることを願っています。
「運動会と体育祭」(違いがわかる辞典 https://chigai-allguide.com/cw0441/ 閲覧日5/15)
「熱中症について学ぼう:暑熱順化」(熱中症ゼロへ https://www.netsuzero.jp/learning/le15 閲覧日2025/4/24)
「【運動会前必見】速く走るためのトレーニング方法、小学生がすぐに足が速くなる方法|動画で解説」(サカイク https://www.sakaiku.jp/column/exercise/2023/014296.html# 閲覧日2025/4/24)
「学校で行われるきっかけは?」(NPO法人 全国ラジオ体操連盟 事務局 https://www.radio-exercises.org/archives/1203 閲覧日2025/4/26)
「消費カロリー40%増 後ろ歩きは早歩きよりも健康に良い」(NATIONAL GEOGRAPHIC https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/25/031400142/ 閲覧日2025/5/7)