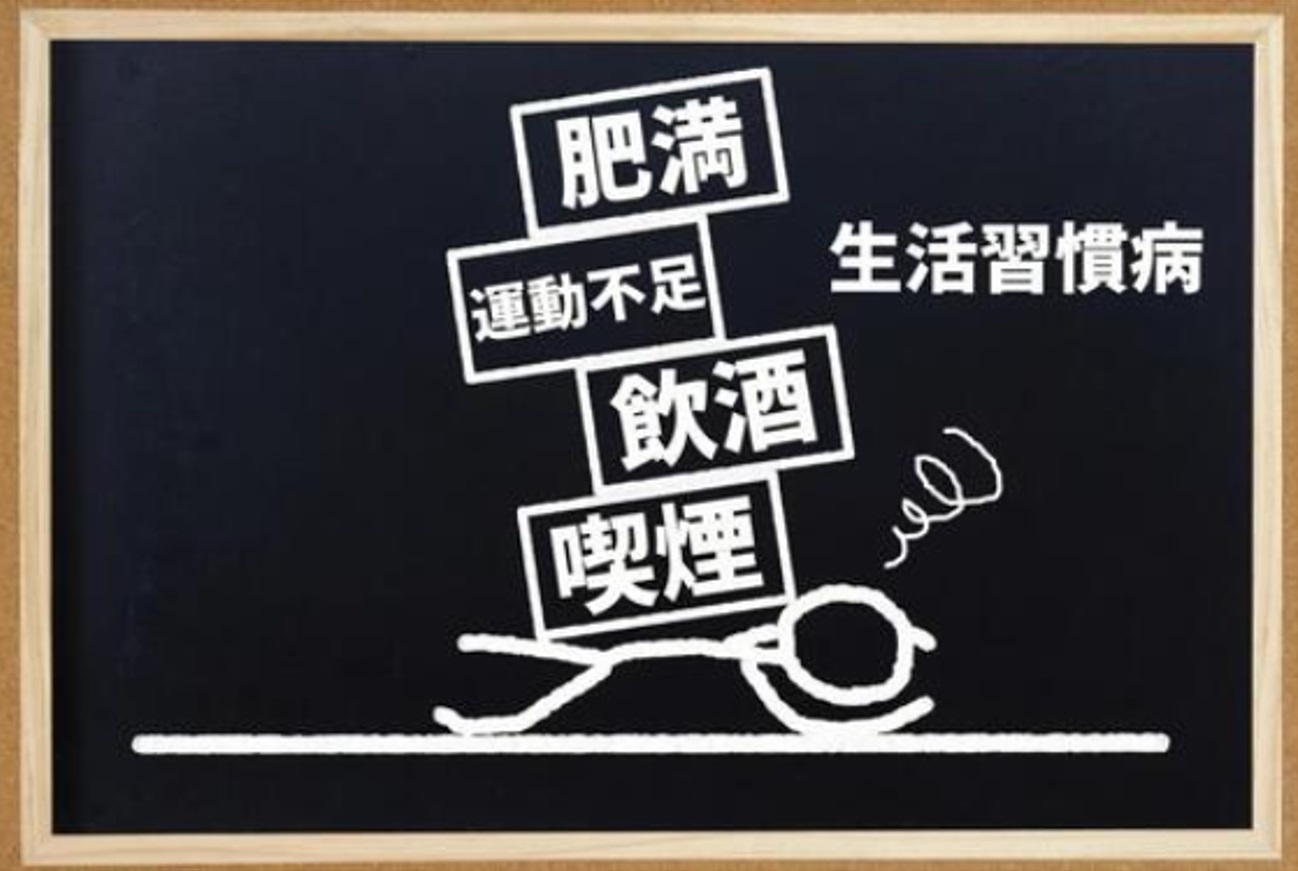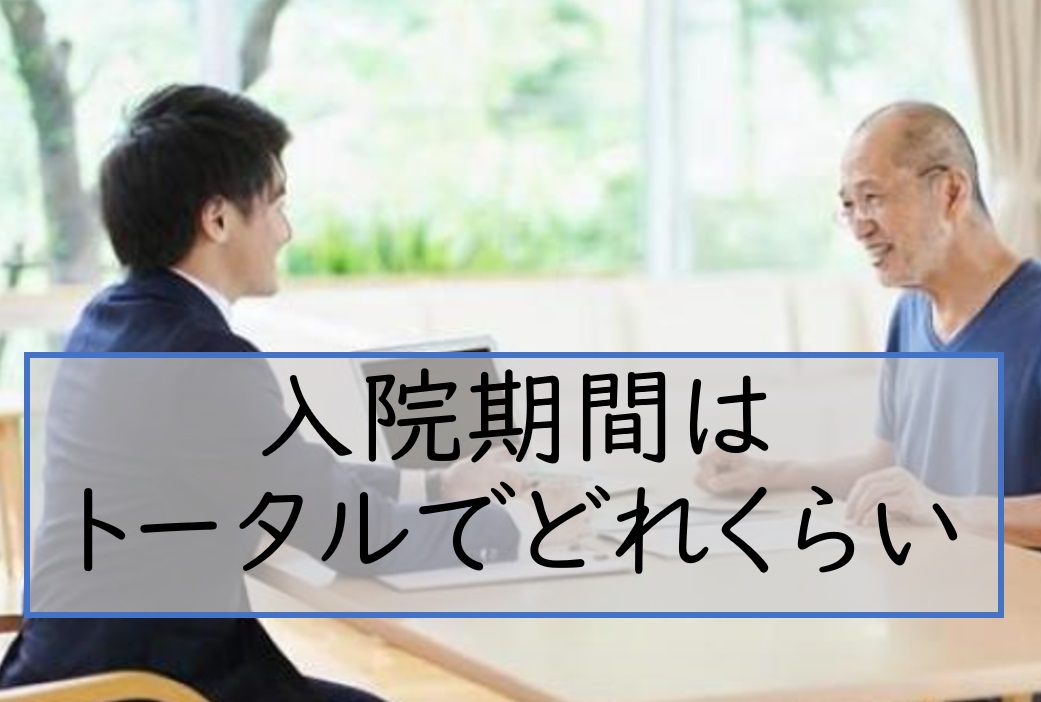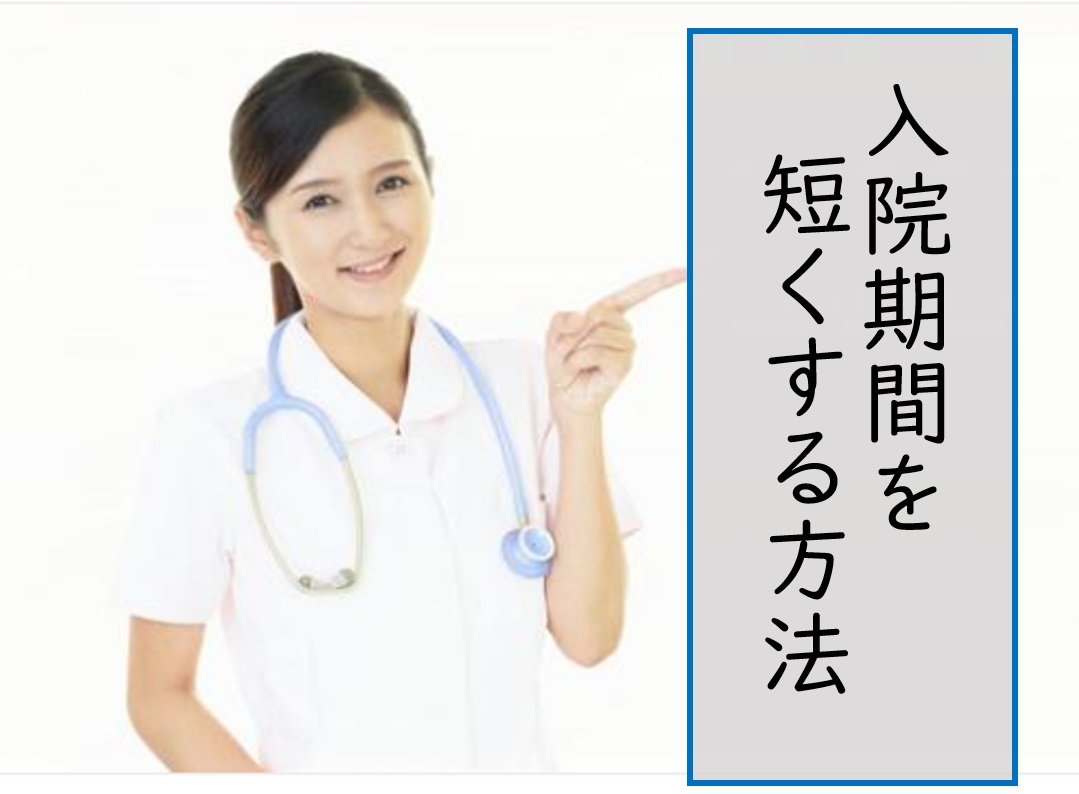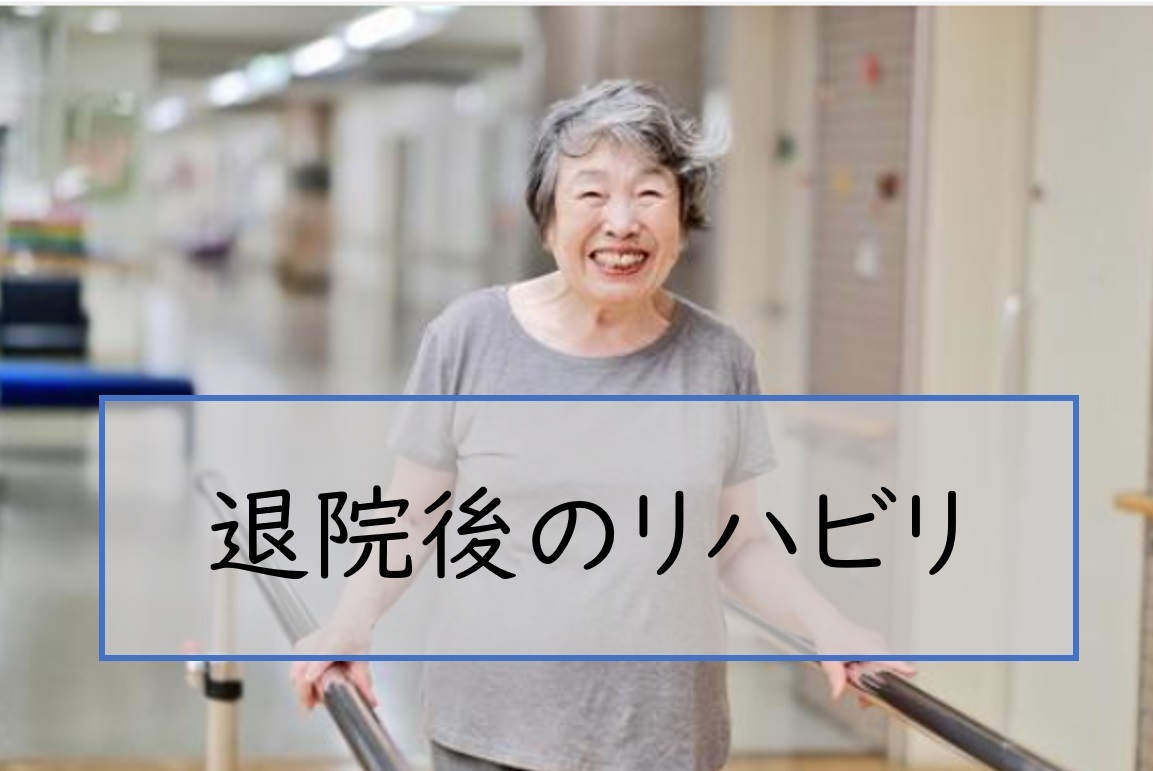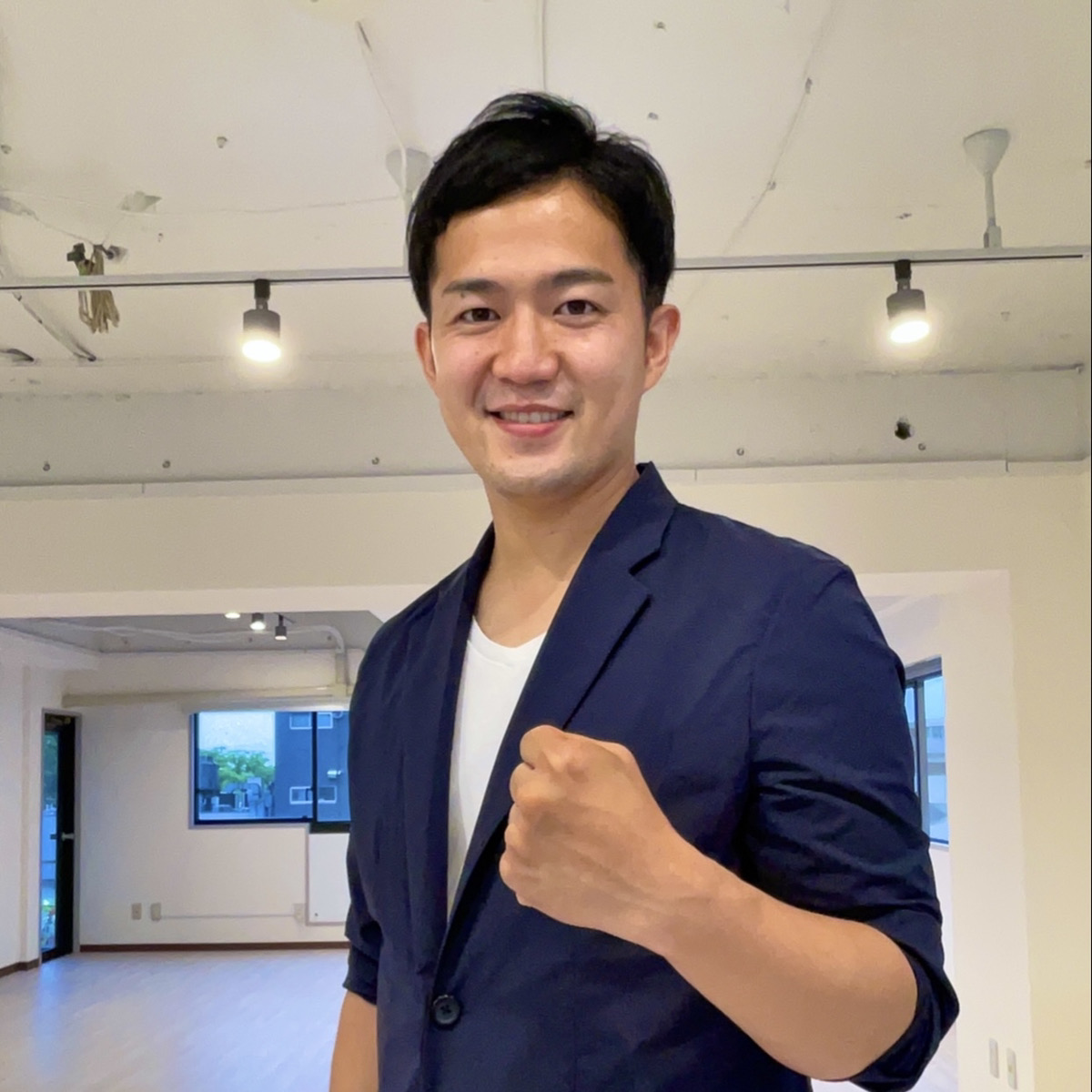脳出血のリハビリに必要な入院期間について

脳出血のリハビリに必要な入院期間について
脳出血や脳梗塞をはじめとする脳血管疾患は内閣府の報告によると要介護の原因の第2位となるなど、再発例も含めて年間で推計29万人発症しています。
内訳としては64%が脳梗塞、25%が脳出血、9%がくも膜下出血とされています。
(『日本の脳卒中の発症者は年間 29 万人―滋賀県脳卒中発症登録事業より推計―』H29滋賀医科大学より)
今回、脳出血をはじめとする脳血管疾患の原因、男女比、入院期間、退院後のリハビリについてまとめてみました。
目次
・脳出血などの脳血管疾患の原因
・脳出血などの脳血管疾患の好発年齢と男女比
・入院期間はトータルでどれくらい
・入院期間を短くする方法
・退院後のリハビリ
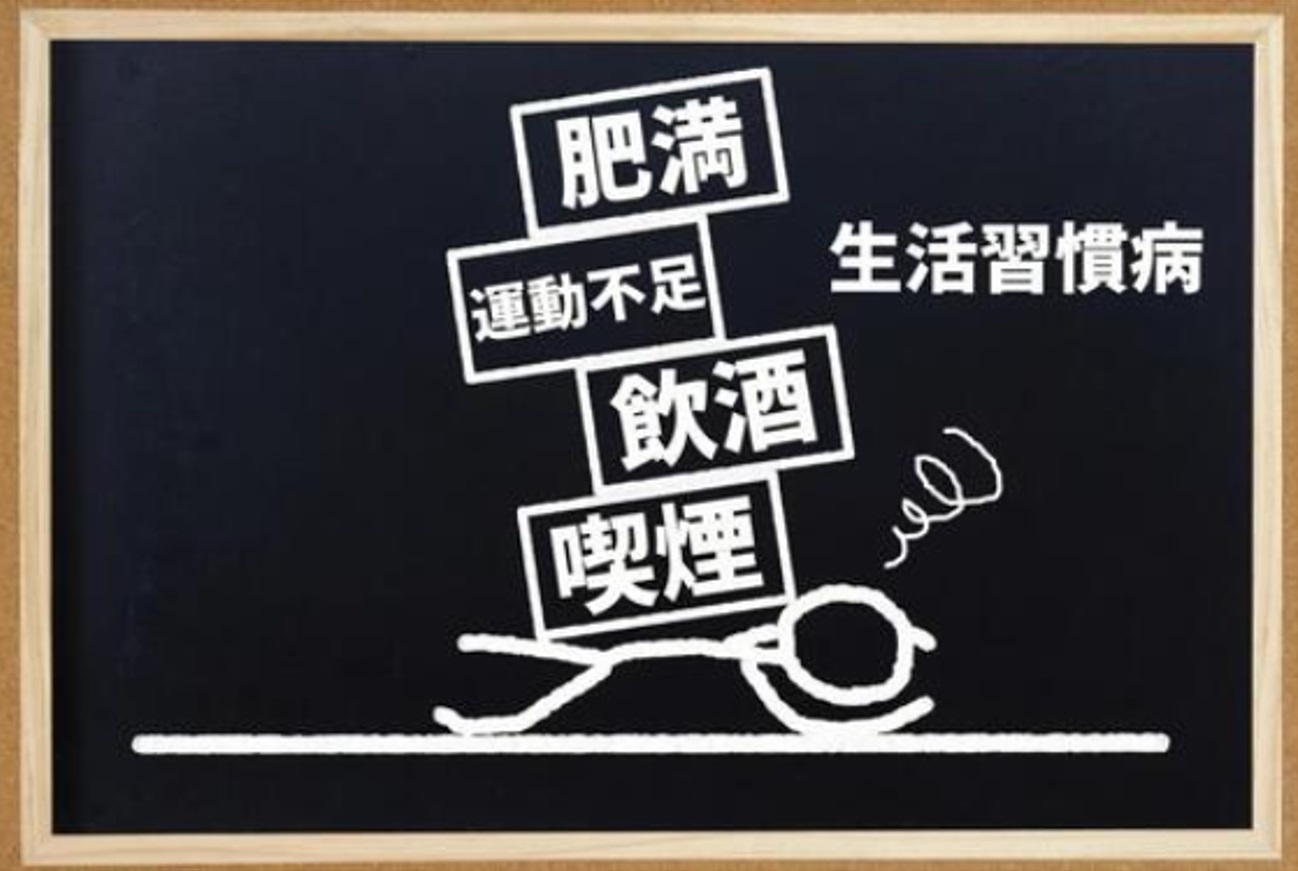
脳出血などの脳血管疾患の原因
脳出血や他の脳血管疾患の原因は、生活習慣病と密接に関連しています。
以下に、生活習慣病と脳血管疾患の関連性を説明します。
これらの生活習慣病が積み重なると、脳血管疾患のリスクが高まります。したがって、健康な生活習慣の実践、バランスの取れた食事、適切な運動、禁煙、定期的な健康診断などが非常に重要です。生活習慣の改善は、脳血管疾患の予防に役立つことが証明されています。

脳出血などの脳血管疾患の好発年齢と男女比
脳出血・脳梗塞・クモ膜下出血にはそれぞれの好発年齢と男女比があります。個々により違いますが、一般的なケースは以下の通りです。
脳出血(Intracerebral Hemorrhage)
くも膜下出血(Subarachnoid Hemorrhage)
これらの脳血管疾患は、年齢、性別、リスク因子、遺伝的要因、地理的要因などによって異なる特徴を持つことがあり、個別の患者においても異なる疫学的特性が見られます。したがって、疾患の発症リスクについては、個別の病歴やリスクファクターに合わせた詳細な評価が必要です。医師や医療専門家に相談し、適切な予防策やスクリーニングに従うことが重要です。
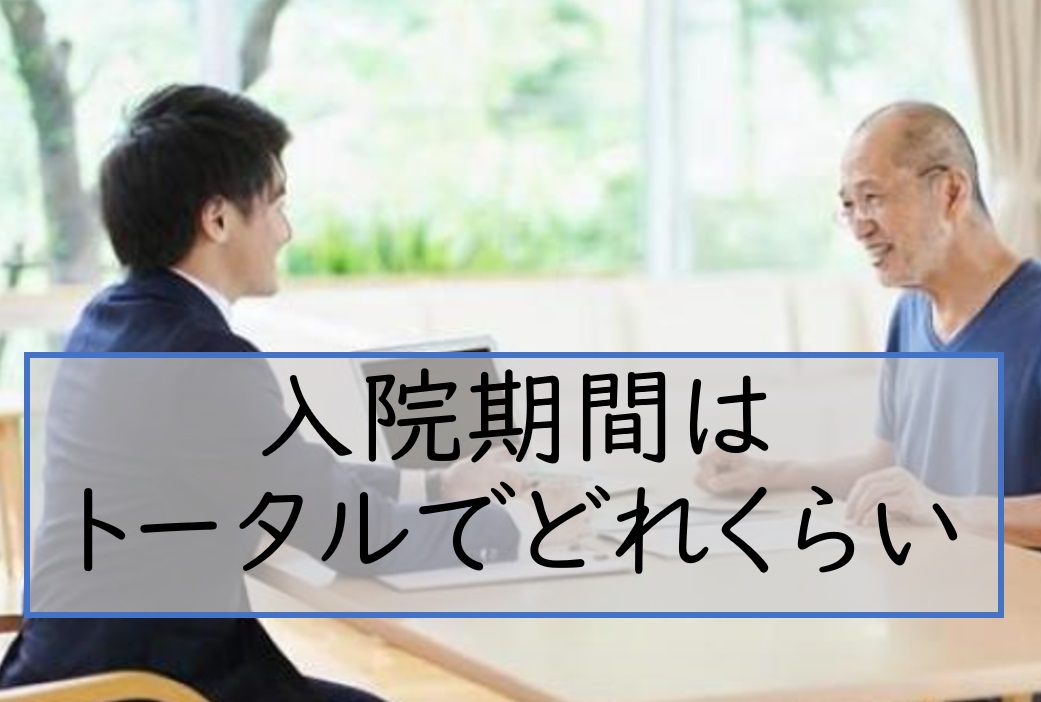
入院期間はトータルでどれくらい
脳出血患者の入院期間は、一般的に急性期(acute phase)と回復期(rehabilitation phase)に経るため、数週間から数ヶ月にわたることがあります。ただし、これは一般的な目安であり、患者の状態や治療計画によって異なります。
回復期(rehabilitation phase)
総合的な入院期間は患者の個別の状態によるものが大きく、治療チームが患者の進捗状況を評価し、ADLの自立度を図りながら退院までの道筋を立てていきます。
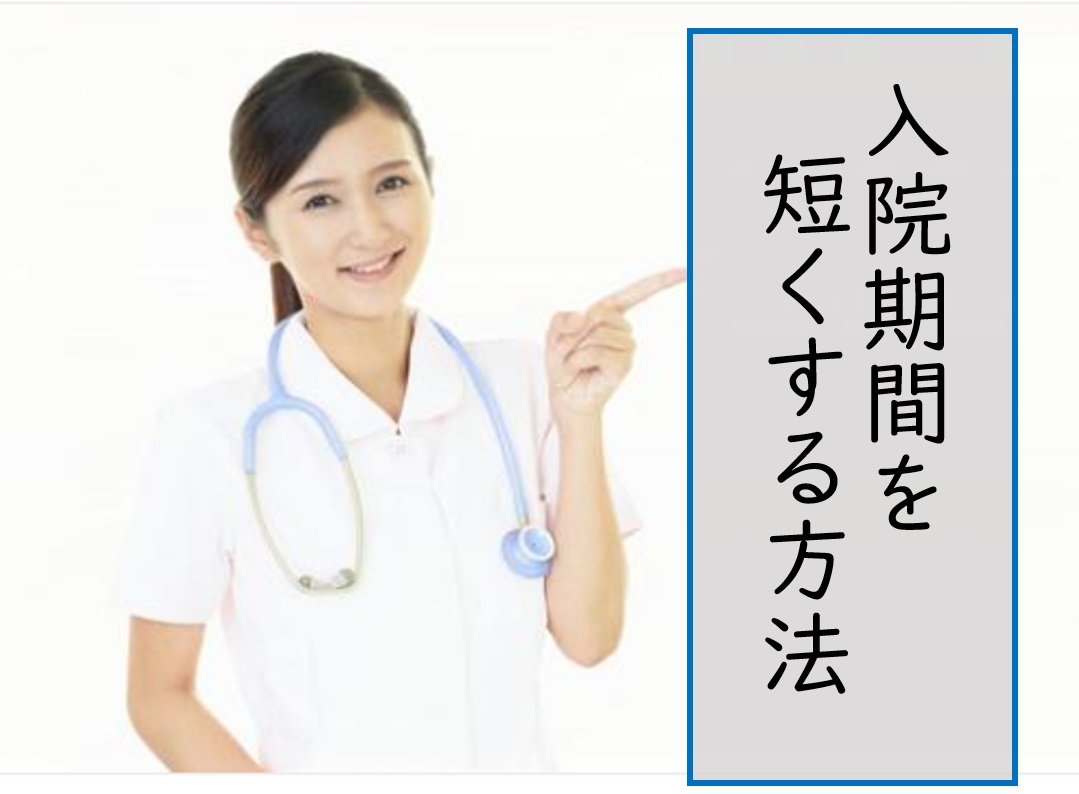
入院期間を短くする方法
脳血管疾患の入院期間を短くするために、リハビリテーションの観点から考えることは非常に重要です。
リハビリテーションは患者の回復を促進し、機能の喪失を最小限に抑え、動作の再獲得をするのに役立ちます。
以下は、リハビリテーションを通じて入院期間を短縮する方法です。
早期リハビリテーションの導入
脳血管疾患の患者に対して、早期にリハビリテーションプログラムを開始します。
急性期からリハビリテーションを始めることで、患者の機能回復を早めることができます。
個別化されたリハビリテーションプラン
各患者の状態とニーズに合わせて、個別化されたリハビリテーションプランを作成します。
患者の障害や機能の喪失に合わせて、運動療法、言語療法、作業療法などの適切なリハビリテーションアプローチを提供します。
家族の教育とサポート
患者の家族にもリハビリテーションに関する情報とサポートを提供します。
家族の理解と協力は、患者の回復を促進する重要な要素です。
目標設定とモニタリング
リハビリテーションプランには、具体的な目標を設定し、それらの進捗を定期的にモニタリングする仕組みが含まれます。
目標の達成度に応じて治療計画を調整し、効果的なリハビリテーションを確保します。
退院計画
退院前に、患者の家庭環境でのリハビリテーションやサポートが計画されます。患者が入院後も適切なリハビリテーションを受けられるように、適切なサービスやリソースが提供されます。
これらのリハビリテーションのアプローチを適切に実施することで、患者の機能回復が促進され、入院期間が短縮される可能性が高まります。ただし、リハビリテーションは患者の状態に合わせて個別化されるべきであり、医師やリハビリテーションチームの指導に従うことが重要です。
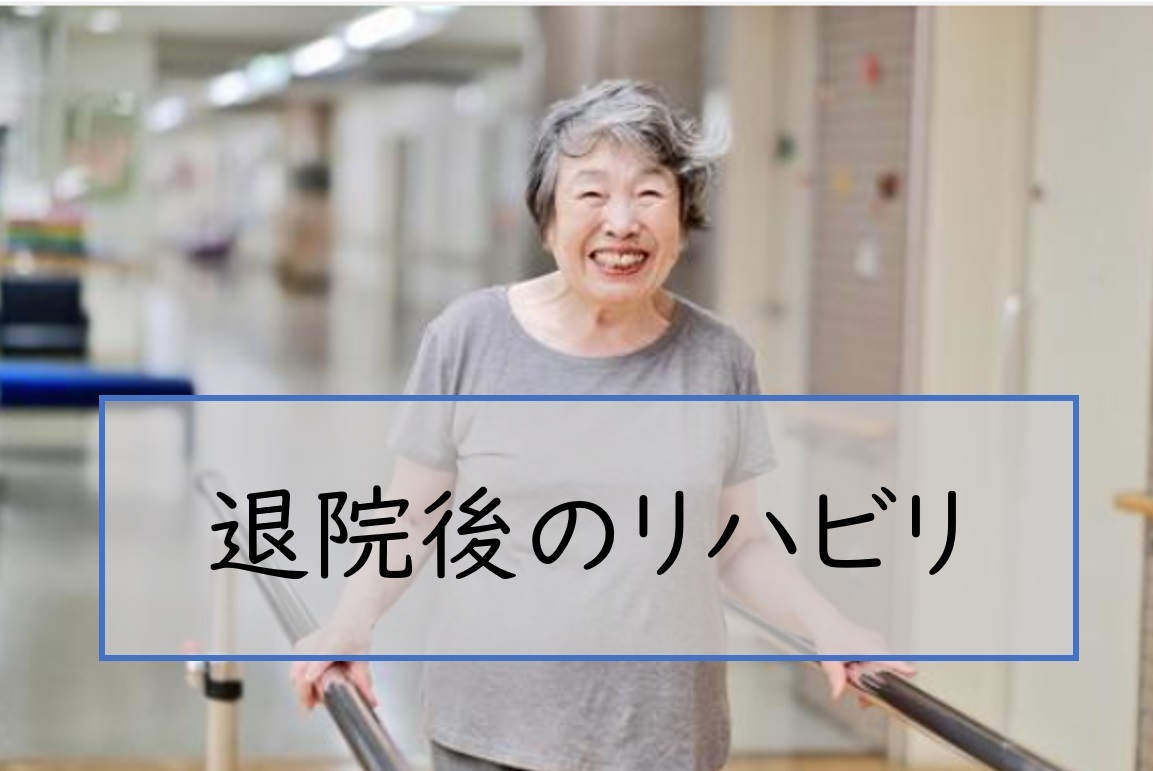
退院後のリハビリ
退院後のリハビリは個別の状態によって変わります。
主な違いとしては介護保険の利用の有無です。
入院中に退院後の生活を見据えて介護保険を申請するケースが多く、訪問診療や訪問看護などの在宅サービスやデイサービスやデイケアといった通所サービスを利用します。
また、介護保険を利用していないケースもあります。それは、申請したが適応外となった方、そもそも介護保険を利用する年齢ではない方、仕事復帰しているため保険サービスを利用することが出来ない方などです。
このような場合、ほとんどの方がリハビリ難民となります。
リハビリ専門家ではない整骨院に行ったり、整形外科クリニックのリハビリも20分程度、医療知識のないスポーツジムなど相談したくても個別の例に対して知識も経験もなく、インターネットやSNSで情報を集めているケースが多いのではないでしょうか。
おすすめは自費リハビリ施設です。
介護保険を利用している方にとっては併用する事ができ、リハビリ時間を増やすことが出来ます。
また、リハビリ難民の方にとっては保険にとらわれない、リハビリを個別に行うため、ケアからトレーニングまで幅広くアドバスをもらうことが出来ます。
職場復帰までのリハビリで週に2-3回通われる方もいらっしゃいます。
施設によっては独自のプランとして宿泊付きもあるようです。
自費のリハビリは社会保障費の増加を背景に国も必要性を認識しており、今後のトレンドとなり、注目されている新しい選択肢となります。
また、再発予防の観点からもアドバイスをすることが出来ます。
リハビリベースの体験は90分の中で内容が充実しています。
よろしければ体験来てください。
リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?
☟お問合せはコチラ☟
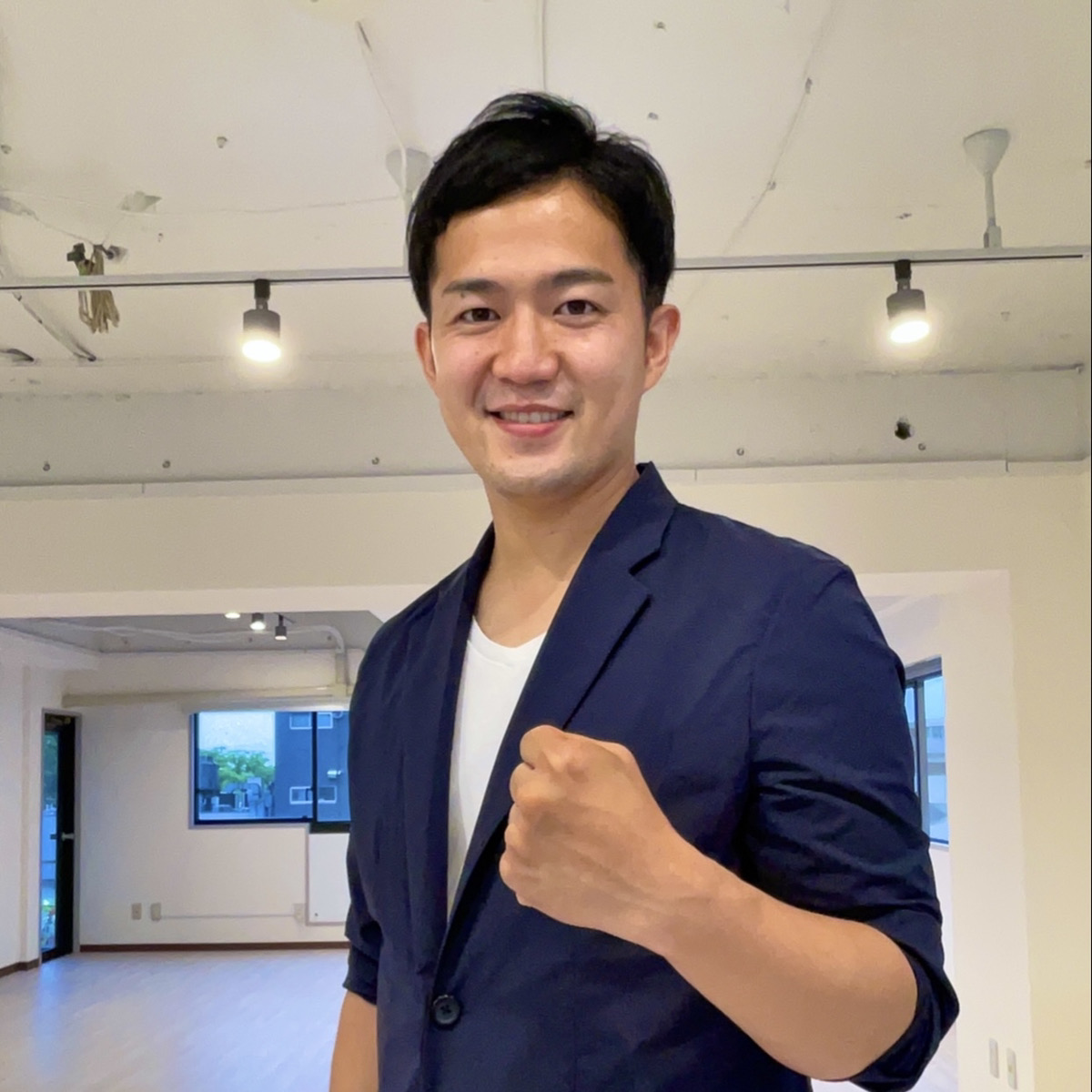
原嶋崇人 リハビリベース国分寺院長 運動器認定理学療法士
小児から高齢者、俳優からスポーツ選手のリハビリを経験。ラグビーワールドカップ2019のスポーツマッサージセラピスト、TOKYO2020大会の医療スタッフとして派遣経験あり。スポーツ現場へのサポート、地域高齢者に対しての介護予防や転倒予防事業の講師などを行っている。